なぜ日本はいじめが多いのか?
突然ですが、自分の意地悪度を知りましょう!
いじめは、子どもだけではなく、大人にも起こりうるものですが、未然防止を図るいじめ早期発見に取り組む社会的問題になっています。
いじめの様態
- 冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- 仲間外れ、集団による無視
- 軽くぶつかられったり、遊ぶふりをして叩かれたり、けられたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、けられたりする
- お金を要求される、カツアゲされる
- お金を隠されたり、盗まれたり、物を壊されたり、捨てられたりする
- 嫌なこと恥ずかしいこと、危険なことをさせられたり、されたりする
- SNSで誹謗中傷や嫌なことをされる
いじめの早期発見⁈

ある教師は、「相手がいやだと思ったらそれはいじめだ」とおっしゃった。
いじめられた側が教師に訴えたところで何の解決にもならず過ごしている子どもはたくさんいます。そして、いじめる側が教師に泣いて「ごめんなさい」をすることで、いじめられた側は泣くこともできず、「大丈夫です」と言うざる負えないケースもあります。
いじめる側が、その場しのぎで泣いて「ごめんなさい」をすると「本人も深く反省している」…という結論にいたります。
いじめられた側が証拠を揃えていたとしても、「かわいそうですけど、学校ではどうすることもできません」とおっしゃる教師もいます。
結局、双方の言い分が違うということになり、特に本人が我慢できるなら、両方の保護者へそれぞれの対応をしているだけで、「いじめ問題が解決したことになった」というケースもあります。
何もかわらない状況に、いじめられても負けない強い子どもになる子もいれば、学校へ来られなくなる子もいますよね。また、いじめた側が学校に来られなくなるケースもあります。
いじめは、どこからが早期発見なんだろう…と考えてしまいます。
実際にSNSで誹謗中傷されている子は、「やめてほしいけど、そこでしか話すことができないんだね。」とあまり気にしていない様子。
また違う子は、両親が学校へ訴えてきて、内容が重大なこともありSNSに載せた子は退学になりました。
人生を左右する「いじめ問題」
いじめは、とても怖いものです。いじめられている子どもは、いじめられているとなかなか言うことができません。心配かけまいと両親には笑顔でふるまっているケースが多い傾向にあります。また、両親へは「いじめられている」と話すのはとても「恥ずかしいし」「情けない」という気持ちもあると言います。
しかし、それは間違っていますよ!と声を大にして言いたいです。
いじめられていることは決して恥ずかしいことではありません。そして、両親はあなたのことが愛おしいのです。あなたが悲しんでいると悲しくなるし、あなたが笑っていると、楽しくなります。最悪の事態を招く前に、ココロを開放してください。
例えそれは、両親じゃなくてもかまいません。「いじめられて苦しい」時は、必ず誰かに相談してください。
そして、周りの大人は「信じられる人」「助けてくれる人」になってください。いじめは、いじめられる側も、いじめる側も辛い状態になります。
声にならない声に気づき、助けを求めている子どもたちに気づくこそが、いじめの早期発見と言えるのではないでしょうか。
いじめ防止の取り組み
- 安心して、他者からも認められている
- 自分が必要とされる存在であると感じること
- 学校や職場が落ち着ける場所になるようにすること
- ストレスや感情をコントロールする力を養うこと
- 自己存在感、自尊感情を高めること
- お互いの違いを認め合い、支え合うこと
- 他者との関わりや役になっていると感じること
- 共同的活動を通じて、活躍できる機会をつくること
- 人間関係を形成する力を養うこと
- 社会性の育成を目指すこと
- 安心して落ち着いて生活をおくることができる環境
- 教室や職場など環境を整備し、自己実現を図る環境
- 生活をしていくうえで、必要な規範意識の向上を目指せる環境
まとめ
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第四条(いじめの禁止)「児童等は、いじめを行ってはならない。」という法律があります。法律までいかずとも、学校側にはいじめ防止を行う義務があります。
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
いじめと遊びの違い
- 1人でも苦しむ人がいて、それをみんなが楽しんでいる
- 相手がきずつくことがわかっていて、「やめて」といっているのにやめない
- 参加したがらない相手を脅したり、暴力をふるうなどして強制参加させている
- 誰かのココロやカラダを傷つけることをする
- からかう側はターゲットをいつも同じにして傷ついているにも関わらずからかい続ける
一つでもあてはまるなら、それは「いじめ」です。
いじめる側もいじめられる側も、両者の話をよく聞き対応していきましょう。
今できることは、あなたの早期発見です。
個々の自我状態を分析してみるのも、一つの解決方法を生み出す方法かもしれません。ココロとカラダを健康に、みんなが人を支えられる人になってほしいと切に願います。
ぜひお試しください。

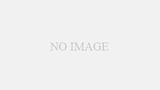





コメント